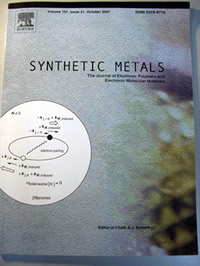超伝導理論をはじめとする物性物理学の研究を行う加藤貴本学大学院新技術創成研究所助教の論文“Intramolecular ring current in (4n+2)π electronic states in the neutral acenes”の図が、Synthetic Metals誌(Elsevier Science)の表紙を飾る図に採用された。
超伝導体とは一般に非常に低温で電気抵抗がゼロになる物質である。室温(298 K (25 ˚C))での実用化のための高温超伝導体の開発を目指した研究は、その学術的な視点のみならず社会にも及ぼしうる重要性から、世界中の物理学者や化学者によって長年にわたって取り組まれてきた。しかし超伝導転移温度(超伝導性が壊される温度)は一般に非常に低く、現在、最高の転移温度をもつ銅酸化物超伝導体でもおよそ135 K (-138 ˚C)程度であり、高温超伝導発現の実現が切望されている。
このような背景により、加藤貴助教は京都大学、マックス・プランク研究所(ドイツ、シュツットガルト)そして本学で長年に亘って、超伝導理論をはじめとする物性物理学の研究を行ってきた。
また、一方で、ベンゼンなどπ共役系芳香族炭化水素分子でミクロサイズ(数オングストローム程度)の分子内においては、磁場を付加させると室温においてでさえ超伝導的な反磁性環電流が誘起されることは、100年近く前から知られている。このことに関連して「ミクロなサイズ(数オングストローム程度)のπ共役系芳香族炭化水素分子における反磁性環電流」と「マクロなサイズ(数センチメートルくらい)の超伝導性(いわゆる世に言う超伝導性)」の2つの現象の間の、矛盾の無い統一的解釈は、非常に大切であるのにも関わらず、これまでに解明されていないどころか、ほとんどの研究者にその重要性にさえ気づかれないまま100年間もの月日が経った。特に、J. A. Pople教授(1998年ノーベル化学賞受賞)をはじめとする世界第一線の理論化学者たちでさえ、1960年代に本研究に取り組んできたが、この問題の真の重要性(固体物理学の観点からは)には気づいていなかったと思われる。
以上のような背景により、加藤貴本学助教は、100年間解明されてこなかった「ミクロなサイズ(数オングストローム程度)とマクロなサイズ(数センチメートルくらい)の物質に起こりうる2つの現象の間の、矛盾の無い統一的解釈」を目標に現在、研究を行っている。そして最近「なぜ、π共役系芳香族炭化水素分子において反磁性環電流が誘起されるのか」という問いに対する新しい仮説を提唱し、また上述の2つの現象が矛盾なく統一的に解釈できる理論を提唱致した。
本研究内容に関連して2007年9月にスペインのペニスコラで開催された超伝導関係の国際学会(7th International Symposium on Crystalline Organic Metals: Superconductors and Ferromagnets 2007)において口頭発表を依頼され、また2007年10月に出版された論文(Synthetic Metals ((2000年、ノーベル化学賞を受賞したA. Heeger教授、A. MacDiarmid教授, 白川英樹教授も編集委員会のメンバー)(Elsevier Science) (157, 793-806 (2007)) “Intramolecular ring current in (4n+2)π electronic states in the neutral acenes”)の中の「反磁性環電流発現機構を説明する図」が学会誌の表紙を飾る図に選出される等、本研究課題の重要性は非常に高いとされる。
もし加藤貴本学助教の仮説が正しければ、以下の3つの大きな課題((a)-(c))が一挙に解決できる可能性もあるという。
(a) 従来の常識であるBCS理論(古くから知られている、いわゆる超伝導発現メカニズムを説明する理論(1957年に提唱され、1972年、ノーベル物理学賞の対象になった理論))では説明できないメカニズムで発現する超伝導体は存在するか?
(b) たった1つの分子内で超伝導性が存在しうるのか?
(c) 室温超伝導体は存在するのか(あるいは合成し実用化できるか)?
また、加藤助教は、2006年12月に出版した「Photochemistry and its Nanoelectronics Applications (光化学とそのナノエレクトロニクスへの応用)」で、この著書の内容に関連して、Transworld Research Network 出版社から“Award of Excellence”も受賞している。
◎関連トピック
/cgi-bin/news/news_view.cgi?KEY=444
◎長崎総合科学大学大学院新技術創成研究所
http://www.nias.jp/center/ri4/index.html
超伝導体とは一般に非常に低温で電気抵抗がゼロになる物質である。室温(298 K (25 ˚C))での実用化のための高温超伝導体の開発を目指した研究は、その学術的な視点のみならず社会にも及ぼしうる重要性から、世界中の物理学者や化学者によって長年にわたって取り組まれてきた。しかし超伝導転移温度(超伝導性が壊される温度)は一般に非常に低く、現在、最高の転移温度をもつ銅酸化物超伝導体でもおよそ135 K (-138 ˚C)程度であり、高温超伝導発現の実現が切望されている。
このような背景により、加藤貴助教は京都大学、マックス・プランク研究所(ドイツ、シュツットガルト)そして本学で長年に亘って、超伝導理論をはじめとする物性物理学の研究を行ってきた。
また、一方で、ベンゼンなどπ共役系芳香族炭化水素分子でミクロサイズ(数オングストローム程度)の分子内においては、磁場を付加させると室温においてでさえ超伝導的な反磁性環電流が誘起されることは、100年近く前から知られている。このことに関連して「ミクロなサイズ(数オングストローム程度)のπ共役系芳香族炭化水素分子における反磁性環電流」と「マクロなサイズ(数センチメートルくらい)の超伝導性(いわゆる世に言う超伝導性)」の2つの現象の間の、矛盾の無い統一的解釈は、非常に大切であるのにも関わらず、これまでに解明されていないどころか、ほとんどの研究者にその重要性にさえ気づかれないまま100年間もの月日が経った。特に、J. A. Pople教授(1998年ノーベル化学賞受賞)をはじめとする世界第一線の理論化学者たちでさえ、1960年代に本研究に取り組んできたが、この問題の真の重要性(固体物理学の観点からは)には気づいていなかったと思われる。
以上のような背景により、加藤貴本学助教は、100年間解明されてこなかった「ミクロなサイズ(数オングストローム程度)とマクロなサイズ(数センチメートルくらい)の物質に起こりうる2つの現象の間の、矛盾の無い統一的解釈」を目標に現在、研究を行っている。そして最近「なぜ、π共役系芳香族炭化水素分子において反磁性環電流が誘起されるのか」という問いに対する新しい仮説を提唱し、また上述の2つの現象が矛盾なく統一的に解釈できる理論を提唱致した。
本研究内容に関連して2007年9月にスペインのペニスコラで開催された超伝導関係の国際学会(7th International Symposium on Crystalline Organic Metals: Superconductors and Ferromagnets 2007)において口頭発表を依頼され、また2007年10月に出版された論文(Synthetic Metals ((2000年、ノーベル化学賞を受賞したA. Heeger教授、A. MacDiarmid教授, 白川英樹教授も編集委員会のメンバー)(Elsevier Science) (157, 793-806 (2007)) “Intramolecular ring current in (4n+2)π electronic states in the neutral acenes”)の中の「反磁性環電流発現機構を説明する図」が学会誌の表紙を飾る図に選出される等、本研究課題の重要性は非常に高いとされる。
もし加藤貴本学助教の仮説が正しければ、以下の3つの大きな課題((a)-(c))が一挙に解決できる可能性もあるという。
(a) 従来の常識であるBCS理論(古くから知られている、いわゆる超伝導発現メカニズムを説明する理論(1957年に提唱され、1972年、ノーベル物理学賞の対象になった理論))では説明できないメカニズムで発現する超伝導体は存在するか?
(b) たった1つの分子内で超伝導性が存在しうるのか?
(c) 室温超伝導体は存在するのか(あるいは合成し実用化できるか)?
また、加藤助教は、2006年12月に出版した「Photochemistry and its Nanoelectronics Applications (光化学とそのナノエレクトロニクスへの応用)」で、この著書の内容に関連して、Transworld Research Network 出版社から“Award of Excellence”も受賞している。
◎関連トピック
/cgi-bin/news/news_view.cgi?KEY=444
◎長崎総合科学大学大学院新技術創成研究所
http://www.nias.jp/center/ri4/index.html
![長崎総合科学大学 [NiAS]](/theme/nias/images/common/logo-header.png)